移植医療と脳死 [脳、心、リハビリ]
子供の国内での移植治療ができないため、海外での移植治療に向かう家族の姿がニュースで取り上げられます。難しい問題と思いますが、海外でもドナーを待つ人がいることを考えると、いつまでも日本の国がこのままであってよいとは思えません。
臓器の移植に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO104.html
臓器の移植に関する法律の見直しに伴う「脳死判定による臓器移植に関する日本医師会の見解」(平成17年3月10日)日本医師会
http://www.med.or.jp/nichikara/hantei.html
下記のサイトの「移植医療とは」で移植医療の現状、脳死の考え方、用語などがまとめられていて、勉強になります。

トランスプラント・コミュニケーション [臓器移植の情報サイト]
http://www.medi-net.or.jp/tcnet/index.html
移植医療とは
http://www.medi-net.or.jp/tcnet/tx.html
「脳障害を生きる人びと」 [脳、心、リハビリ]
警察庁は交通事故を死者数、それも24時間死者数で評価し続けています。医療の高度化で24時間死者数の意味合いはその統計が最初に取られた時と大きく変わっていて、同一に比較できないはずなのですが、誤解される統計と思います。気になってこれを調べ始めたら、下記の元NHK記者で現在フリーランス・ジャーナリストの中村尚樹氏の著書にも調べたものが文中に紹介されているのを見つけました。脳障害の様々な事例が紹介され、医療のあり方についても考えさせられます。
警察庁(統計)
http://www.npa.go.jp/toukei/index.htm
脳の可塑性と記憶 [脳、心、リハビリ]
科学ジャーナリスト塾で「脳と心とロボット」という題でグループ演習に取り組んでいます。
その中で「脳の可塑性」という言葉の意味が大きくなってきました。そこで本を調べ始めてであった本が下記の「脳の可塑性と記憶」。1985年、御巣鷹山へ墜落した日航ジャンボジェット機に乗り合わせていて亡くなられた世界を代表する脳科学者であった塚原仲晃先生の執筆中の残された原稿を補い、発行されたとのことです。
1987年から77名の研究者で3年間にわたって実施の研究プロジェクト「神経回路網の可塑性」の総責任者を予定されていただけに、その損失の大きさが伺われます。
ブレインサイエンス振興財団
http://www.bs-f.jp/
塚原仲晃記念賞
http://www.bs-f.jp/tsukahara.html
「日本せきずい基金」の本 [脳、心、リハビリ]
厚生労働省の「身体障害児・者実態調査」(平成13年)によれば、せき髄損傷児・者の合計は11.3万人を数えます。毎年、5000人くらいの方がせき髄を損傷されているといわれます。労災病院における脊髄損傷疫学調査 (1996年度~2001年度)によれば、せきずい損傷にいたる原因は、交通事故が38%、転落が33%、起立歩行時の転倒が9%、そして下敷・落下物、スポーツ、自殺企画などが続きます。
交通事故総合分析センターの集計によれば、平成17年の人身事故件数は92万件、負傷者数は113万人。日本の人口1億2700万人から年間1000人に約9人( ! )が負傷し、負傷者1000人に対して1.6人がせきずい損傷を被ることになります。この受傷者には自動車に追突されたり、はねられたりなどの様々な被害者が含まれることから、大きな問題です。
受傷で脊椎(骨の部分)を骨折していても、せき髄は無事の場合もあり、事故直後、誤った受傷者の取扱いによってせき髄を損傷させないことが必要です。このことを積極的に広報する姿勢が現在の行政に欠けているようにみられます。総務省、また、日本自動車工業会などがこの活動に積極的に取り組むことを願わずにいられません。
NPO法人日本せきずい基金から次の2冊の本をはじめ、様々なせきずい損傷に関連する文献が刊行されていて電子媒体として閲覧できます。
是非、多くの方に読んで理解を深めてもらいたいと思います。
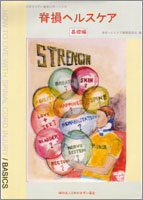
脊損ヘルスケア・基礎編(日本せきずい基金)

脊損ヘルスケア・Q&A編 (日本せきずい基金)
特定非営利活動法人日本せきずい基金
http://www.jscf.org/jscf/
【参考資料】
厚生労働省の「身体障害児・者実態調査」(平成13年)http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0808-2.html
http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h18hakusho/zenbun/pdf/pdf/02_01_01.pdf
労災病院における脊髄損傷疫学調査 (1996年度~2001年度)
http://www.lwc-eirec.go.jp/toukei-center.html
(財)交通事故総合分析センター (ITARDA)
http://www.itarda.or.jp/jp_home.htm
「医用電子生体工学ME事典」 [脳、心、リハビリ]
2005年4月1日に日本生体医工学会となった日本エム・イー学会、下記のWebサイトの紹介に記載されていますが、その分野の英語名(medical electronics、medical engineering、biological engineering、bio-medical engineeringなど)に対して適切な日本語訳がないため、エム・イーという言葉を使ったとのこと。「医用電子生体工学ME事典」(下の写真)は、いきつけの古書店で入手したもので「I 概説」、「Ⅱ 用語」、「Ⅲ 資料」で構成され、「記述が30年前のもの」ということに留意しながら読む必要はありますが、そのⅠ編は全体像を把握するのに有用で記載の内容の多くが現在でも通用するように思えます。*
事典でMEの学問体系として、生体計測工学、生体情報処理工学、生体モデル工学、生体作用工学、生体代行工学、医用系統工学という分類例の他、さまざまなものがあげられていますが、学際性の高い領域であることがわかります。基本的に医療機関などの非常に専門性の高い分野での応用を中心とし、一般の人には馴染みの少ないものであったのが、今日、MRIをはじめとしたその分野の成果がマスメディアを通して多くの人の目に触れるようになってきたように思います。また、学際的な研究を通じて、今後、さらに多くの成果が生まれることが期待されます。
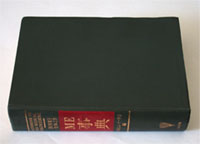
日本エム・イー学会編 「医用電子生体工学ME事典」、842ページ、1978、コロナ社
社団法人日本生体医工学会
http://www.jsmbe.or.jp/
* 「ME教科書シリーズ」
http://www.jsmbe.or.jp/journal/me-kyoka.html
・ ME分野の本格的な勉強のために
「脳」ブームのあやうさ (理研BSI ) [脳、心、リハビリ]
理研BSIは1997年発足の新しい組織組織で2005年現在、400名以上の研究者が活動しているとのこと。 下記のWebに紹介の記事は色々と勉強になります。その中の「脳」ブームに関する津本リーダーの記事、多くの人に読んでもらいたいと思い、リンクして紹介します。
独立行政法人 理化学研究所 脳科学総合研究センター(理研BSI)
http://www.brain.riken.go.jp/index_j.html
[RIKEN BSI NEWS No.33]
神経回路メカニズム研究グループ 津本研究ユニット ユニットリーダー 津本忠治
「脳」ブームのあやうさ
http://www.brain.riken.go.jp/bsi-news/bsinews33/no33/network.html
"Brain Story" (脳の探究) [脳、心、リハビリ]
英国王立研究所所長、また、オックスフォード大学薬理学教授の筆者が、BBCの『脳の話』シリーズの企画に対して、放映できなかった内容を加えてまとめたが下記の本。ホヤは幼生では脳があるが成長するとなくなるとか、様々な脳疾患の事例が紹介されるなど興味深い本です。そしてパーキンソン病およびアルツハイマー病研究の第一人者とのことですが、これらの神経変性疾患についてもわかりやすく記載されています。
少し前の本となりますが、脳について興味が湧いたら最初に手にすべき本かもしれません。
* * * 下記は原書 * * *
「進化しすぎた脳」 [脳、心、リハビリ]
著者が慶應義塾ニューヨーク学院高等部で8人の中高生を対象に全4回、10日間にわたって行った脳科学講義の内容をまとめたのが本書。副題の「中高生と語る[大脳生理学の最前線]」はこれが理由。会話中の文章で自分で話すように読むと、なぜか理解が深まる気がします。
本書の「はじめに」でファインマンの言葉として紹介される「高校生レベルの知識層に説明して伝えることができなければ、その人は科学を理解しているとは言えない」という言葉、なかなか重いものがあります。
(NHKスペシャル「立花隆・最前線報告・サイボーグ技術が人類を変える」で登場したリモコンネズミの原理、サルがロボットアームを動かす原理についても触れられています。)
新・脳の探検 [脳、心、リハビリ]
脊髄損傷者支援イベント「Walk Again 2006」 [脳、心、リハビリ]
10月9日、横浜ランドマークホールで特定非営利活動法人日本せきずい基金の主催により、標題のイベントが開催されます。第1部の「脳科学から運動機能再建へ;新しいアプローチ」では、この分野の第一線の研究者による講演が続きます。早速、参加申し込みしました。
特定非営利活動法人日本せきずい基金
http://www.jscf.org/jscf/
【私の手にした脊髄損傷に関する本】
脊髄損傷("Spinal Cord Injury")についてはっきりと知ったのは、書名は忘れてしまったのですがプールの飛び込みで脊髄損傷となった女性の名前を題名とした自叙伝(確か、妹の口述筆記)のペーパーバックを読んでからでした。もう四半世紀くらい前のこと。そして1年ほど前のことですが、医療関係者でもないのに、いきつけの古書店で次の本を目にし、写真、図が多数収録されて理解しやすく、今日、リハビリテション医学やそれを支える工学などによって環境はかわりつつあるとしても、記載の様々な障害の内容は今日も共通であることから、レジに向かっていました。

今井銀四郎編著「脊髄損傷ハンドブック〔改訂版〕」、1988年7月、新地書房








